説明
<目次>(一部抜粋)
序章 コロナ危機と教育の現場
Withコロナ時代、日本はどこへ向かうのか
コロナ危機の時代に求められる「主体性」
コロナ危機は旧来の教育理念を見直す好機
忍耐は練達を生じ、練達は希望を生じる
第1章 コロナ時代の教育に求められるもの
情報の海を泳ぎ切る力
露呈した「ハイテク後進国・日本」の姿
膨らむ「電子書籍」のニーズ
総合知に対立する博識
「言霊の幸わう国」はどこへ行った?
考える力を低下させるオーバーカリキュラム
コラム「みどり児」
第2章 「ヒト」は教育によって「人」になる
能動的な学び「アクティブ・ラーニング」
固定観念にとらわれない発想を
非常識なるがゆえに教育的価値がある
AI時代に求められる「要約力」
羅針盤のない船のように漂う日本の教育
生を感じるこころ
「公平の原則」について考える
エリート校化する中高一貫校
人は何のために学ぶのか
競争と協調
「3つのM」に動かされるな
公教育の目的は「公人」の育成
コラム「番号のない卒業証書」
第3章 教師という仕事について考える
教師の生きがい
知り合いに教員はいますか?
教師を辞めたいと思った時
薄れる「教師に対する信頼と敬意」
教員の過重労働で支えられる公教育
全人教育の評価は数値化できない
教員採用試験で重視される「人物試験」
教師は「聖職者」である
教員の不祥事を発生させないために
コラム「人生の選択」
第4章 受験と英語教育とクリティカル・シンキング
なぜ小学校から英語をやるのか
「大学入学共通テスト」で問われるもの
「探究」は教育改革の要
なぜ今「クリティカル・シンキング」なのか
求められる「メタ認知」と「内省」の力
自分の考えを論理的に表明する「外化」の能力
グローバル・コンピテンシー(国際標準知)の時代
なぜ英語4技能が必要なのか
コンテント・ベース(内容中心型)の英語指導法
コラム「内的決断」
第5章 アメリカと日本の公教育政策
アメリカの「公教育」崩壊の教訓
グローバリズムは終焉したのか
公教育は「福祉」である
公教育階層化の歴史的流れ
方策としての公教育の私事化
教育とは未来への投資である
コラム「楽観のすすめ」
第6章 21世紀の教育はどうあるべきか
「21世紀スキル」とは何か
個別最適化教育への道
全寮制教育で「個」を育てる
数値化できない学力に目を向けよ
効果的な学びの原理「PEAK」
教える(Teaching)から手助け(Facilitating)する教師へ
コロナ危機で進む「オンライン授業」への移行
「DX時代」の公教育
21世紀の教師像
教室での議論は「フェイスブック型」から「ツイッター型」へ
コラム「壁を好機ととらえよ」
【著者紹介】
岩崎 充益(いわさき みつます)
1949年長野県生まれ。長野県立下伊那農業高校卒業後、東京教育大学(現筑波大学)に入学。在学中に箱根駅伝でアンカーを走る。卒業後、世界放浪し37ヵ国に滞在する。帰国後、獨協大学外国語学部ドイツ語学科卒業、米国コロンビア大学大学院で英語教授法の修士取得。その後、横浜の私立山手学院高校、東京都立高校で英語を教える。全寮制都立秋川高校の舎監長、都立五日市高校校長、都立青山高校校長をへて、現在、東京都教育庁指導部高等学校教育指導課 特任教授、獨協大学非常勤講師を務める。
主な著作に『都立秋川高校 玉成寮のサムライたち』『「公教育」の私事化 -日本教育のゆくえ-』がある。
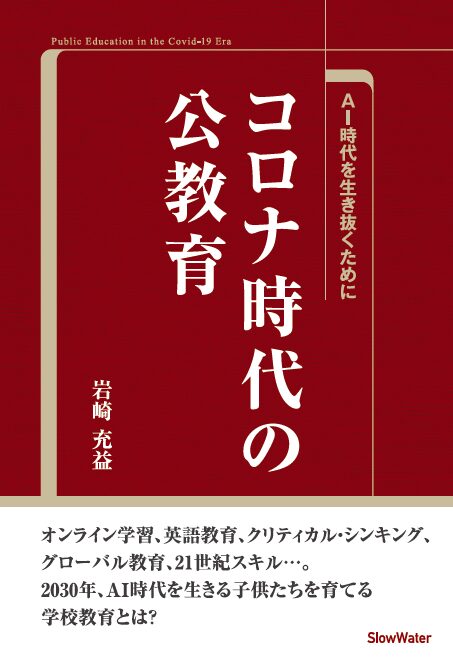

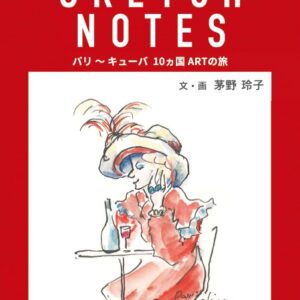
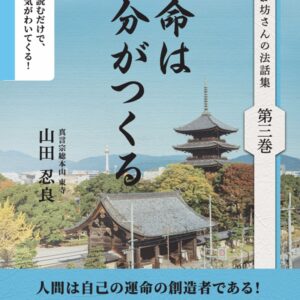
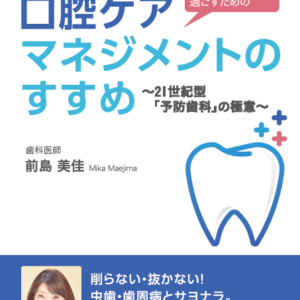
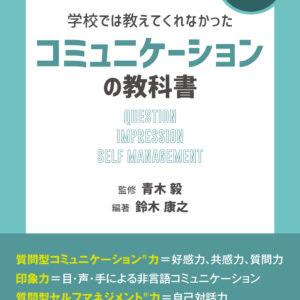
レビュー
There are no reviews yet. Be the first one to write one.